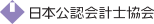あの頃不思議に思ったことは・・・
『ダイバーシティ』という言葉をご存知ですか。今や多くの企業に取り入れられ、関心度は非常に高くなっています。多様性、すなわち人種・宗教・性別等の枠を超えて広く人材を登用することにより、様々な意見が集まり、そこで議論することによって、より良いものを生み出すというものです。企業活動が国際化して、遠く離れた地域の出来事が企業活動に影響を与え、また消費者のニーズが多様になった現在は、これらの変容に柔軟に対応するために、『ダイバーシティ』が必要な時代と言えるのです。
欧米諸国とは異なり、日本では人種・宗教の差がほとんどなく、女性の雇用や役職者登用などに内容が絞られる傾向にありますが、決して女性の問題に限られたものではありません。老若男女、様々な立場・経験・環境の人間が集まることで、それぞれの意見が衝突すると期待され、その際、信念を持って議論を重ねることにより、その企業組織の進むべき道が見えてくるという、組織そのものの問題なのです。同じ思考回路の人間が集まって結論を出すよりも通常は煩雑で時間がかかり、決して楽な方法ではありません。
さて、“意見が衝突する”と言いましたが、先日拝聴したあるセミナーでは、一つの問題が指摘されていました。日本企業の構成員は、長くその組織に属することにより一定の企業風土に染まっているため、新たに登用しても衝突するような意見が出難いというのです。意見が衝突すれば効果があるというものでもなく、究極的にその企業のためになることを進言できなければ意味は無いのですが、たとえ立場が異なっても、皆同じ思考回路では、柔軟で有効な意見への期待は低くなります。
社会に出たばかりの頃、“変だな”、“なぜこうなるのだろう”と思ったことはありませんか?今、その問題についてどのように感じていますか?疑問すら持たず、当たり前のことになってはいないでしょうか。企業経営は経営者が舵を取りますが、構成員の個々の意識もまた、組織を維持発展させていくための大切な力になっています。“本当に必要なことは何なのか”を個々人が考え、主張する力を時代は求めているようです。
広報委員会委員 鈴木 真紀恵
(2010.4.1 データ更新)